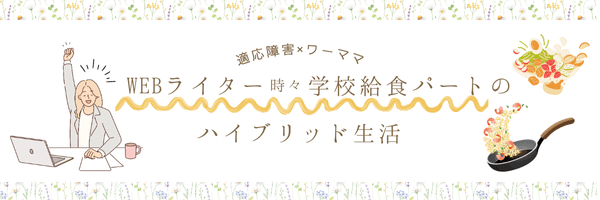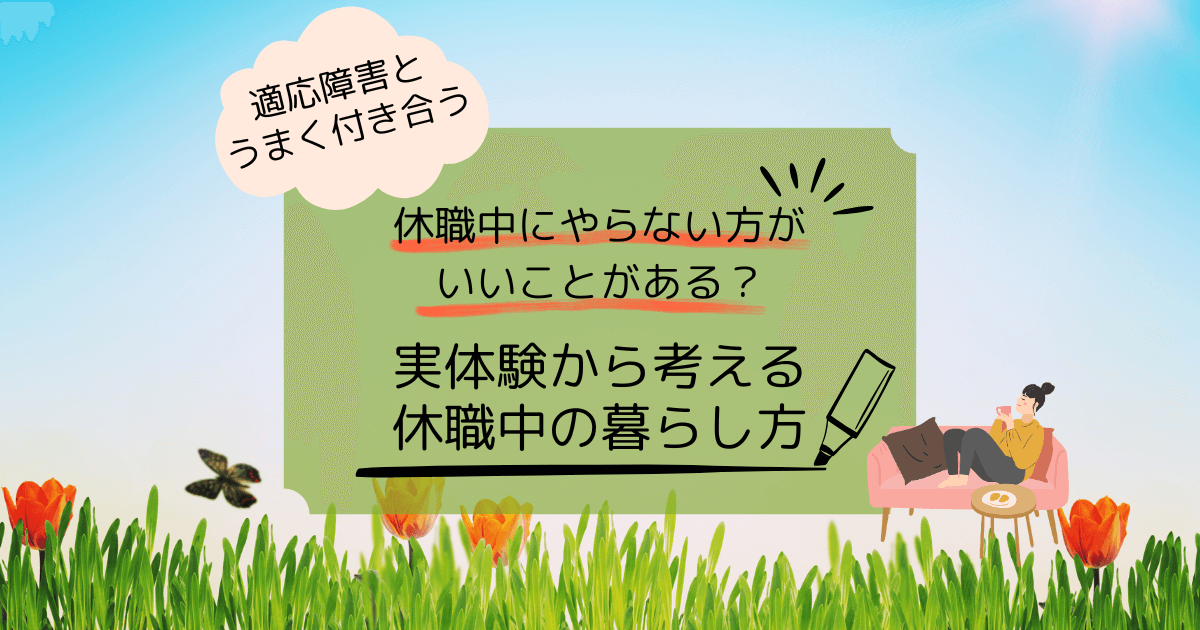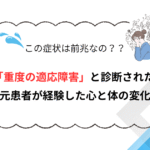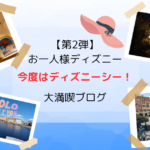本記事には広告・プロモーションが含まれています。

仕事が原因で適応障害になった私は、2度の休職を経て退職。今は個人事業主のWEBライター&学校給食パートとして働いています。
今は元気に生活していますが、生き方の基盤を作ったのがまさに「休職中」でした。
休職中ってただ休んでいるわけではなく、自分の生き方を見直す良いきっかけになると思うんですね。今まさに休職している方は「そんな悠長なもんじゃない!」って思うかもしれませんが、今となっては【休職中の過ごし方は今後の人生に大きな影響を与えるものだ】と痛感しています。
ハッキリ言って、私は休職中の過ごし方に関しては大成功したと思っている人です。そのおかげで、今は家族の協力もあって自由に、心の平穏を守りつつ生きています。
今回の記事では、元患者が考える「今後の人生をより良くできる休職中の過ごし方」を解説します。
休職中にやらない方がいいこと3選

休職してすぐは心に余裕がないものですが、仕事などストレスの原因から離れて時間が経つと、だんだん心が安定してきます。結果として「何かしたいな」という意欲も出てくる方も多いでしょう。
意欲が出るのはとても良いことで回復の兆しとも思えますが、ここで「何をするか」を間違えると今後の生活や治療に影響が出ることもあります。まずは、休職中にやらない方が良かったこと・私がやって後悔したことを3つ紹介します。
SNS(Facebookやインスタ)

これは暇に耐えかねて見ることもありましたが、あまりおすすめしません。
Facebookで見るアカウントは以前からの友人がほとんどですが、みんな順調に働き、子育てをし、プライベートも充実して…といった、今の自分とはかけ離れたキラキラ生活を送っているのを見てしまうからです。
もちろん、その裏でたくさん泣いたり辛い思いをしたりしているのでしょう。でも、休職中の自分にとってはまぶしすぎて、勝手にみじめな思いをするのでやめた方が無難です。
インスタは見知らぬ人が映える写真を投稿しているものですよね。

見ていてぐったりするので、Facebook以上に避けるようになりました。
一方で、X(当時はTwitter)は同じように苦しんでいる方が投稿しており、共感できる部分も多々ありました。同じく適応障害で悩んでいる方にコメントしたり、コメントされたり、結構楽しく見ていたのはXでしたね。
ただ、自分以上に過酷な状況にいる方もいて、心がネガティブな方に引っ張られることもありました。そこだけは注意ですね。
資格取得の勉強

これは「時間があるからやろう!」と思っていましたが、クリニックのカウンセリングで相談したら即却下されたものです(笑)。
要するに、ストレスの原因になった仕事に直結するものは、休職中にやるにはふさわしくないとのことです。

言われるまで全然気が付きませんでしたが、すぐに仕事に結びつくものばかり思いつく自分を見て、適応障害になった理由の片鱗が見えた気がしました…。
ちなみに、仕事がダメなら家族が食べるおかずを作り置きしようと思いましたが、これもあまりおすすめされず。休職中は「誰かの役に立つこと」ではなく、「自分だけが楽しめること」をやることを心がけるようにアドバイスされました。

私がカウンセリングから得たものはこちらの記事でも紹介しています。
-
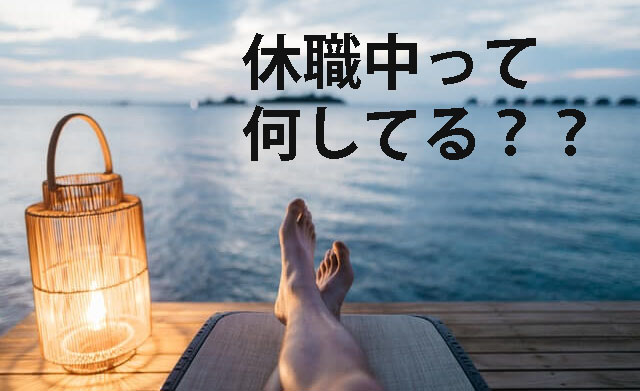
-
適応障害で休職中の過ごし方 カウンセリング金言から考えてみる
本記事には広告・プロモーションが含まれています。 適応障害の治療目的で約3年にわたって心療内科に通院していた私は、当時医師の診察以外に「カウンセリング」を受けていました。 メンタル疾患は、薬を飲んで治 ...
続きを見る
これは今でも肝に銘じていることで、仕事以外に自分にしか利益のない趣味を持つようにしました。私の趣味は舞台鑑賞とひとりディズニー、ダイアモンドアートですね。この3つは適応障害になった後から始めたものです。
ひとりディズニーの様子はこちらでも紹介しています。
-
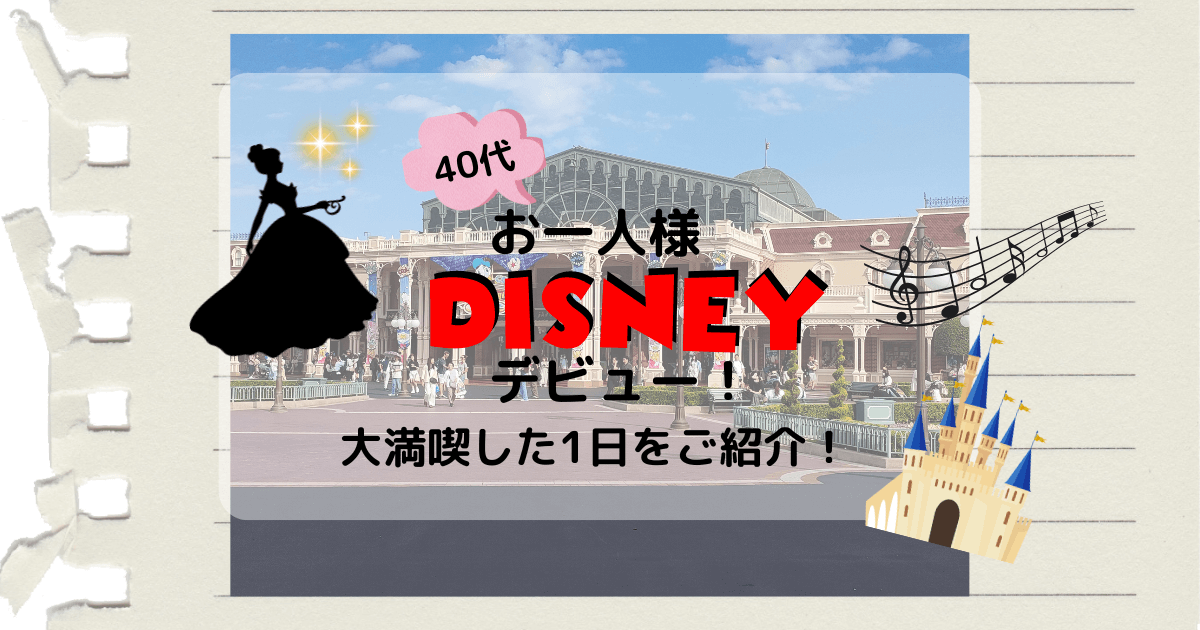
-
40代女性のお一人様ディズニーデビュー!想像以上に快適でメンタル整った
本記事には広告・プロモーションが含まれています。 こんにちは!ぴょん吉です! 実は先日、パートが休み&ライターの案件も全部納品済みという久々の完全フリー日がありまして、前々から挑戦してみたかっ ...
続きを見る
ダイアモンドアートは、粘着がついたシートに色とりどりのビーズをひたすらペタペタ貼っていく手芸です。それこそ、インスタなどでよく見かけたやつですね。

暴飲暴食

これはねぇ…。ストレスたまっていると食べたくなっちゃうので仕方ないんですけど、コントロールできるなら控えた方がいいと思います。
ある程度回復してくると食欲も出てくるので、つい何か食べたくなっちゃうんですよね。散歩ついでにコンビニによってスイーツなんか買っちゃうと本当にやばい。

私は休職直後に全然食べられなくて、2ヶ月で7kg近く痩せました。ただ、回復するにつれてだんだん食べられるようになり、夫もその様子が嬉しくていろいろ買ってきてくれたり、ランチに連れ出してくれるわけです。
その結果として、回復した今にダイエットを頑張ってもなかなか痩せない(笑)。回復して調子こいた自分が恨めしいです。
これは個人差があるので何とも言えないですし、人によっては贅沢な話に聞こえるかもしれません。あくまで私のお話として聞いてもらえるとありがたいです。
休職中の過ごし方Q&A
ここからは「これはやっても大丈夫?」といった疑問をまとめてみました。
旅行は行ってもいい?

私は全然OKだと思います。実際、私も当初から予定していた家族でお泊りディズニーに行ってきました。
ただ、何点か注意点があります。
体力・気力は落ちていることを自覚する
元気になったつもりでも、休職したことで体力や気力が以前よりも落ちている可能性も高いです。無理のない行程を組み、一緒に行く方にもきちんと理解をしてもらいましょう。
私も思った以上に疲れが出てしまい、15時過ぎにホテルでチェックインして少し仮眠してから再入園しました。子どもがまだ小さかったので、一緒にお昼寝をしていた感じです。
また、一人旅の場合は途中で誰かに頼ることもできません。こまめに休憩を取りつつ、責任を持って無事に帰れるように設定するのが大事です。
旅行の様子をSNSに上げる
どこで誰が見ているか分からず、職場の人に思いがけず見られてしまうかもしれません。
「病気で休んでいるって聞いたのに!」と、復職後に余計なトラブルになる可能性もあるため、自分のなかだけで楽しむ方がいいかと思います。
お金を遣い過ぎない
休職から復職して長く働ければいいですが、私のように退職する可能性もまだまだあります。久しぶりの旅行でテンションが上がってしまうかもしれませんが、あまり散財しすぎず、今後の生活も考えて計画的に旅行を楽しみましょう。
職場に行く練習はした方がいい?

これは復職日が正式に決定してからでいいと思います。休職中はとにかく焦らず、心と体の回復だけに専念しましょう。
前述の通り、仕事を連想させるものは極力避けた方が無難です。回復途中の心に余計な負荷をかける必要もないので、職場のことはいったん忘れて生活してくださいね。
私は復職が決まってから、電車が空いている時間や実際の通勤時間帯にお試しで行ってみました。
復職初日に向けた準備の様子は、こちらの記事でもくわしく紹介しています。
-
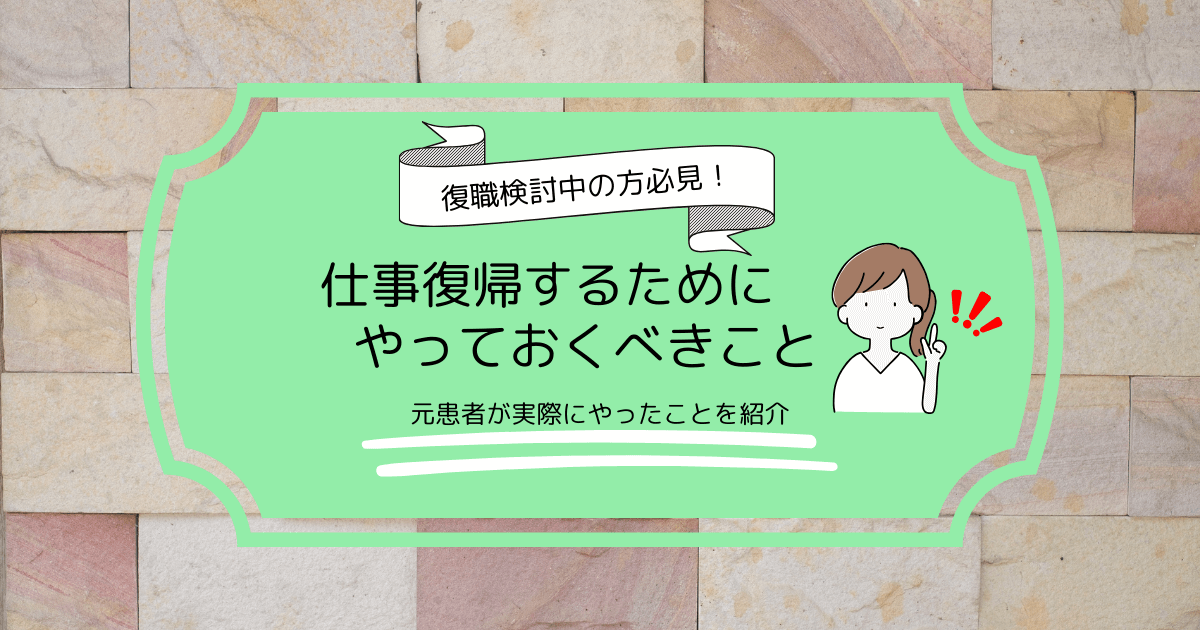
-
【適応障害の復職準備】元患者が初日に向けてやったことをまとめました
本記事には広告・プロモーションが含まれています。 ぴょん吉 こんにちは!ぴょん吉です! 適応障害で休職中の方にとって、一番ドキドキするタイミングが「職場への復帰初日」ではないでしょうか。 私も同じで、 ...
続きを見る
復職日はいつ決める?

回復のために休職したものの、「いつまで休めばいい?」と気になっている方もいるのではないでしょうか。職場によって規定が違いますが、休職できる期間の上限もあるので復職のめどを立てておきたい気持ちもありますよね。
ただ、あまり焦ってもいいことはありません。長く休職するのも不安かもしれませんが、見切り発車で復職すると再発してしまい、今よりもさらにきつい思いをする可能性も否定できないからです。
実際、私も再発して2度目の休職をしたときは、1回目のときよりも処方薬の容量が増えてしまいました。毎日飲む薬に加えて頓服も出され、それもあっという間になくなってしまう始末。うまく復職できたと思っていましたが、やはり焦りがあったのかもしれないと後悔しています。
私が主治医から言われた「復職できるタイミング3か条」は下記の通りです。
復職できるタイミング3か条
- 睡眠と覚醒のバランスが取れている
- 仕事以外の日常生活が何の問題もなくできる
- 「そろそろ働きたい」と自然に思える
この3か条については、私が適応障害を発症するに至った経緯などを書いた記事でも紹介しています。私のストーリーが長々と書いてあるので、お時間があるときにでもどうぞ。
-
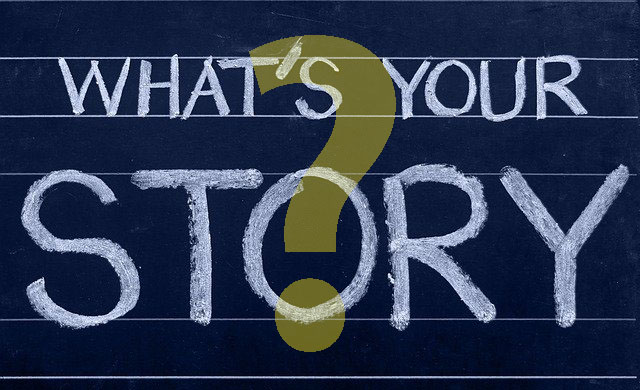
-
なんで「適応障害」を発症しちゃったの? そもそものお話と今のお話
本記事には広告・プロモーションが含まれています。 突然我が身に降り掛かってきた「適応障害」。 適応障害って、こころの病気?ワタシが!?なんで?何をどこで間違えたらそうなるの?? 発症してから約3年心療 ...
続きを見る
まとめ
休職中の過ごし方は非常に重要で、どう過ごすかで今後の人生が決まると言ってもいいくらいです。適応障害の回復スピードはもちろん、自分との上手な付き合い方も見えてくるので、復職するにしろ退職するにしろ、無理なく生きる方法を見つける良いチャンスだと思います。
まずは焦らず休むこと、やれることから少しずつ動くこと、自分だけが楽しめる趣味を見つけることなどがおすすめです。

医師や臨床心理士など専門家のアドバイスも受けつつ、穏やかな毎日を過ごせますように。